4. 「なぜ、難燃化するのか」の真実・・・ほとんど誤って考えている
新しい結果を得るためには、今までの常識を一度、覆した方が良い。特に非ハロゲン難燃剤の研究は1960年代からおこなわれ、さらに1980年から約20年間、多くの研究がされていずれも失敗している。この節では、少し強引ではあるが、「今までの常識を一度、覆してみる」という試みをする。
4.1. 炭素が燃えるの間違い
すでに指摘したが、炭素がリッチな燃料である石炭などの印象が強いために、普通は炭素が燃えて二酸化炭素になるのが燃焼であると考えられがちである。しかし、石炭に直接火をつけるのはかなり困難で最初は薪などより燃えやすいものに火をつけて十分にストーブが加熱したら石炭を投入することから判るように炭素は燃えにくい。Fenimoreが1963年に最初に指摘した表 2 5は未だに示唆的である。炭素の固まりであるスス。表面積も大きく薄いススが火炎の中を通って舞い上がることを考えると炭素が燃えにくいことも頷ける。
表 2 4 Femimoreの酸素指数研究


図 2-11 ほとんど分解しない高分子はもえるか?

図 2-12 成形などの条件によって構造が変化するものもある

図 2-13 PET/red-Pの酸素指数変化
表 2-5 PBTとPCにred-Pを加えたときの加熱残渣の元素組成



図 2-14 PPに対するフィラーの混合量と発熱量(左:見かけ。右:補正)

図 2-15 水酸化アルミニウムと炭酸カルシウムの配合量と酸素指数

図 2-16 「燃えないもの」の分解開始温度と吸熱量の関係
 +
+ (4)
(4)

図 2-17 ポリエチレン樹脂と水酸化アルミニウムの燃焼熱の関係

図 2-18 APP/PER

図 2-19 APP/PERを用いたPPの発熱抑制(50kW/m2)
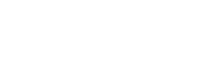
図 2-20 熱分解温度と燃焼
新しい結果を得るためには、今までの常識を一度、覆した方が良い。特に非ハロゲン難燃剤の研究は1960年代からおこなわれ、さらに1980年から約20年間、多くの研究がされていずれも失敗している。この節では、少し強引ではあるが、「今までの常識を一度、覆してみる」という試みをする。
4.1. 炭素が燃えるの間違い
すでに指摘したが、炭素がリッチな燃料である石炭などの印象が強いために、普通は炭素が燃えて二酸化炭素になるのが燃焼であると考えられがちである。しかし、石炭に直接火をつけるのはかなり困難で最初は薪などより燃えやすいものに火をつけて十分にストーブが加熱したら石炭を投入することから判るように炭素は燃えにくい。Fenimoreが1963年に最初に指摘した表 2 5は未だに示唆的である。炭素の固まりであるスス。表面積も大きく薄いススが火炎の中を通って舞い上がることを考えると炭素が燃えにくいことも頷ける。

4.2. 炭化層の形成が難燃性をもたらすということの間違い
燃焼表面には炭化層が形成される。そして炭素は燃えにくいので「表面に炭化層を形成すると燃焼を抑制しうる」といわれる。確かにコーンカロリメーターでPCの燃焼時の発熱速度を測定すると炭化層が形成され、それがはじけるとまた燃焼が激しくなる。このことから長い間、炭化層の形成が難燃性を高めると考えられてきたが、それも疑わしい。表面の炭化層がかなり頑丈で緻密であれば内部からの分解ガスの噴出を抑制することができるが、多くの高分子の表面にはそれほど明確な炭化層は形成していない。むしろ炭化物を形成することによって総分解ガス量が減少すると考えた方が良い。たとえばポリイミドの熱分解曲線は少し奇妙だが、この高分子が燃えないことはよく理解できる。600℃から700℃で熱分解するものの分解量は20%程度にしかすぎず、燃料不足である。

まだ再現性がないが、少しの処理で熱分解が極端に抑制される例がある。よく「成形後は燃焼しにくくなる」ということを経験するが、図 2-10などもその一例である 。

4.3. 「リンは炭化を促進する」の間違い
同じ高分子でも炭化を促進する代表例がリンであり、ポリエステルに使用される赤リンがそれにあたるとされている。確かにPETに赤リンを混練すると酸素指数が上昇する。


このデータなどを元に「ポリエステルに対して赤リンが炭化層の形成を助ける」と言われている。しかし、図1-22でも判るように赤リンを加えたものでも残渣量はほとんど変化がない。それを高分子側から分析した結果を図 2-4に示す。PBTは加熱によって徐々に酸素と水素が少なくなり、炭素リッチな構造に変化している。これに赤リンを加えると、C/H比は増大せず、逆に低下している。これに対して炭化して難燃化を示す典型的なプラスチックであるPCは赤リンを添加しない場合、800℃でC/H比が5程度であるのに対して、赤リンを入れると15にもなる。このことから「PCについては赤リンを加えることによって炭化物が増加するがPBTでは別のメカニズムと考えた方が良い」。しかし、実験をしているとどうしても「確定的な理由をつけたい」という欲求がわいてきて、難燃化されると「炭化が進んだから」とレポートされることが多い。
4.4. 燃えないものを入れるの間違い
燃焼反応は短い時間で起こる。その間に難燃剤と高分子が反応して燃焼を阻害する。このようなことから長い間、難燃剤の相溶性や分散が話題になってきた。難燃剤の相溶性が良いと難燃反応には望ましいが、可塑剤のようなものが大量にプラスチックに入るので耐熱性を落としたり、強度が低下するなどの問題を生じる。プラスチックにとっては熱変形温度は非常に重要な性能であり、それが少し(具体的には1,2℃でも)低下するのは実用的な見地からも望ましくないのである。
一方、炭酸カルシウムのようにプラスチックに溶解せず、堅いものはプラスチックのコストを低下させ、剛性を高めるが、構造的な欠陥の原因となり衝撃強度の低下が懸念される。さらに、燃焼開始とともに高分子表面が後退し、無機化合物が表面に露出する。すでに温度が高く高分子内部は溶融しているので液体状の分解生成物が毛細管現象で表面に供給され燃焼は加速される。このようなプラスチックに無機物を混入させて燃焼を抑制しようとする試みは古くはルイ王朝時代のフランスから行われ、特に第二次世界大戦後、ポリエステル関係の難燃性を高めるために研究が盛んに行われた 10) 11)。特に、水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウムは熱分解温度が高分子の熱分解温度より少し低く、しかも吸熱反応であることから、①水酸化アルミニウムなどの無機物自体が燃えない ②分解の時に吸熱して燃焼熱を緩和する ③分解反応の時に水を放出する ④一般的にプラスチックより安価なものが多い などの理由で有望な難燃剤と考えられた。しかし、実際に研究が進んでみると効果は少なく、60%もの混練量が必要でありプラスチックの特性を著しく落とす領域になることが判ってきたのはこのような原因が「裏」にあるからである。


図 1-28は示唆的なグラフである。PPにフィラーを混合すると右の図に見られるようにコーンカロリメーターの見かけの発熱量は比例して減少する。しかし、フィラーを入れた分だけは発熱量は減少するはずであるという仮定をおいて計算すると左の図のように水酸化マグネシウム以外はむしろ発熱量は高くなっている。このように燃えないものを入れて、本体の高分子がよけいに燃えやすくなる。すでにロウソクには芯があり、石油ストーブのガラス芯が古くなると綺麗に燃焼しないことは判っているが、なかなかそれと結びつくことはない。
このことは結果的に大量の難燃剤を混練しなければならない結果をもたらす。図 1-29はそれを端的に示した図であり、本来20%程度も燃焼ガスが減少したら燃焼の抑制は可能なのに、50%近い量が必要とされる。

粒形をかなり小さくしていくと別の効果が出てくる。今様に言えば「ナノテク」である。この技術は本稿では「新しい技術」のところに収録した。
4.5. 吸熱反応の間違い

そのもの自体は燃焼しない無機化合物を入れてもそれほど効果が無いことがわかったが、それでも水酸化アルミニウムなどはかなりの難燃効果がある。そこで、熱分解反応は式(13)で示されるように水を放出する吸熱反応であることにその理由が求められた。

論理としてはそれも良いのだが、実際に計算してみると図 2-9に示したように燃焼のエンタルピーは水酸化アルミニウム等の無機水酸化合物が熱分解するときの吸熱エンタルピーに対して桁違いに小さいことである。従って吸熱反応は燃焼の抑制に寄与しない。それでも水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウムは、明らかに炭酸カルシウムなどより難燃効果が高い。このような疑問をもって実験する学者は日本には少ないが、アメリカやヨーロッパにはいる。その一人にInnesさんとあってお話をしたら、「吸熱反応が効果があるのではなく、分解温度が低いので、分解する時に溶融した中間生成物が材料表面を多い、その色が白色に近いので、輻射熱による伝熱量が減少するから」と説明された。簡単な説明ではあるが、残念ながらすぐマニュアル化する日本人との差を感じた。「吸熱量にポイントがあるのではなく、昇温途中に分解などをする化合物が良い」ということになれば、また別のアイディアもわく。
4.6. 断熱層形成の間違い
「イントメッセント系」が1980年代初頭に発見された。この原理は「一般的に二つの化合物が材料表面に炭化した泡の層を作り、断熱効果で燃焼を抑制する」とされた。その代表的なものがAPP/PERで、下式の2つの化合物を使う。

PPはきわめて難燃化が難しい材料であるが、この方法では難燃化が可能である。

これも実際に計算してみると、ガスの熱伝導率は温度の上昇とともに高くなり、一方、液体の熱伝導率が低くなるので、燃焼温度の500℃程度では断熱効果は顕著ではない。むしろ、酸化反応場と分解場の間の距離が長くなり、そのために伝熱量が減少する方が大きい。
4.7. 燃えるものは燃えるの間違い
これまでの難燃機構を考え直すのは上記の6項目程度であるが、付け加えて2つの現象を考えてみる。一つは「プラスチックは燃える」「材木は燃える」という印象が強いが、それは「普遍的事実ではなく、ある特定の条件下で燃焼する」という程度に考えた方が良い。たとえば、一般的な構造のポリアリレートが燃えるかと聞かれて直ちに答えられる人は少ない。またPCにPPFBS(後述)を100ppm加えて燃えなくなるか?と質問されれば、燃えると答える人の方が多い。現実にはこのいずれも燃えない。
「・・・は燃えるのだから」と考えずに、少しでも変化させれば燃えなくなると考えて再スタートするのも良いかも知れない。
4.8. 熱分解と重量減少の錯覚
室温から徐々に温度を上げていくと、長時間の劣化実験条件付近の温度を経験する。この温度では急速な崩壊は発生しないが、それでもある程度の分解は起こっていると考えられる。さらにガラス転移温度、成形温度を経て高分子は溶融状態になる。成形温度条件での高分子のかなり激しい劣化は成形工場などでよく観測される。そしてポリフェニレンエーテルの場合には370℃付近で高分子鎖の一部が転移反応により構造が変化し、より分解しやすくなる 12)。
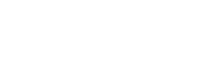
そしてついに分解温度に接近し急速に高分子が分解するように見える。しかし、実際の所はどの温度で高分子が分解しているのかは定かではない。つまりTGAなどの熱分解機器で測定されるものは揮発したものであり、図 2 8の下に示したように単量体は100-200℃の沸点、二量体は500-550℃の沸点を持つ。従って、熱分解温度として観測される550℃付近ではすでに全ての高分子鎖が三量体になっているとしても矛盾は起こらないのである。
4.3. 既存の難燃剤を使ってどこまで改善できるか?
(脱線)学問というもの
学問、特に自然科学や工学は「新しいことを発見したり、これまでにないものを作り出す」ことを目的としている。仮にすべてが現状でよいということになると、学問が不要になるということは無いが、それに従事している人は極端に少なくて良くなるだろう。それでは「新しいことを発見する」ということはどういうことかをもう一度考えてみると、その多くは「これまでの考えの中に無い、あるいはこれまでの考えとは異なる新しい考え方」から出てくる。現在の考え方のままで新しいものを発見するというのはその分野の研究が拡大段階にあり、一つの指導原理での研究がまだ終了していない場合に限定される。そのような過渡的な期間はそれほど長くは無いので、やはり新しい指導原理が出てくることが学問には大切なことになる。
難燃材料は19世紀初頭に一度研究され、二度目に本格的に研究されたのは第二次世界大戦の時であった。それ以来、膨大な研究がなされてきた。対象となる材料はプラスチック、ゴム、繊維などを合計しても20種類程度しか無く、これまでに発見された難燃化の主要な方法は4種類である。従って、80種類の研究をすればそれでおおよそのことは判明する。研究対象物がこのように少なく、研究年限が長い場合であって、新しいものが出現しないときには学問は現状を否定して取りかかるものである。
このような考え方から、難燃材料の研究の歴史と、私たちが研究対象として使うことのできるカード、つまり研究の指導原理を次の様にまとめることができる。1940年台に第二次世界大戦の中でアメリカ軍がハロゲン(塩素化パラフィン)・アンチモン(酸化アンチモン)を発見した。当時はまだポリエチレンの重合がうまくいかなかった時代で、高分子量のハロゲン化合物は使用されなかった。1960年台には不飽和ポリエステルの難燃研究などを通じて「燃えないもの」としての無機化合物を混練する方法が開発された。現在の水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムがこれに相当する。さらに1963年のFenimoreの酸素指数測定法の開発によって炭化に関する研究が進み、1970年代にvan Krevelenらが高分子構造と炭化層の研究を、Factorらが炭化の研究を進めて、リン化合物を使用する一連の難燃材料が出現した。そして1980年代初頭になると、燃焼材料表面に発泡層を形成するという新しいアイディアが登場し、イントメッセント系という特殊な呼称で分類されるようになった。この方法は物理的な難燃化方法ともいえるもので、それまで難燃化が困難であったPP(ポリプロピレン)などを難燃化する強力な方法と考えられた。
レイチェル・カーソンが「沈黙の春」を出版したのが1963年であり、出版当時は「人間の行為が自然に影響を及ぼすはずはない。自然はもっともっと大きい」という反論が産業界から強かったが、1972年にMITのメドウスが「成長の限界」を発表するに至って、資源・環境問題は一気に学問や産業界を律するほどのテーマになった。1980年代より難燃研究も環境問題とは不即不離の関係になり、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本のいわゆる3極の研究者たちが、「脱ハロゲン」「非ハロゲン系難燃剤」の開発を集中して実施した。
それから20年間の膨大な努力の結果、現在でももっとも優れた難燃剤はハロゲン系化合物と酸化アンチモンの組み合わせである。ハロゲンがダイオキシンをはじめとした毒性物質と考えられたものの発生源として、アンチモンが発ガン性を疑われている社会環境の中でも、この素晴らしい難燃剤を打ち破る新しい難燃剤は出現しなかったのである。ハロゲン難燃剤を製造している会社にとっては代換えの新しい難燃剤が出現しないことは、あるいは歓迎されるべきことかも知れないが、研究とはより良いものが生まれることであり、その産業が発展するのは古いものを凌駕する新しいものが誕生することである。その意味では、ハロゲン難燃剤を製造している企業にとってもハロゲン難燃剤に変わる優れた難燃剤が出てくることは大局的には必ずしも悪いことでは無いのである。
しかし、「なぜ、今でもハロゲンか?」という疑問に対して真正面から答える試みこそが新しい難燃材料を生み出すもっとも早い方法であろう。ハロゲンに変わる難燃化の研究は、1)炭化を促進する、2)燃焼時の材料の表面状態を変えること などを中心として行われ、具体的な方法としては、1)リン化合物 2)イントメッセント系 3)無機化合物を複合的に使用する 4)シリコン、硼素、窒素を含む化合物などを添加する などが主要なものであった。これらの多くの試みが失敗したという事実としては、1)1980年以降の研究者の能力がそれ以前の研究者の能力より低かった 2)実験の数が少なかった 3)具体的な実験条件が不適切であった などがその原因となると考えられるが、これらはいずれも事実ではない。研究者の能力はそれほど変化がないだろうし、実験の数は膨大で、実験条件はむしろそれまでの研究結果を踏まえているので優れているともいえる。
従って、「なぜ、今でもハロゲンか?」という問いに対しては、「ハロゲン、リン、無機化合物、イントメッセント、シリコンとシリカ、硼素、炭化層、断熱層、不燃物混練」のキーワードは本質的に「ハロゲンとアンチモン」というキーワードに勝てないことを示していると考えるのが妥当だろう。