― 人工材料の自己修復 次のポリマーへ ―
大腸菌の自己修復の勉強から始まって、ポリフェニレンエーテルをモデル材料に選び、このポリマーが一度、洗浄して乾燥した後、再び重合することがわかった。単量体からの重合では高分子同士は酸化的に重合するが、高分子になると下に示すキノン-ケタール反応で分子が伸びていくとされていた。
.jpg)
だから一度洗浄したポリマーの分子量を伸ばすのは、酸素も酸素を運ぶ役割をする銅の触媒もあまり必要ではないのかと思ったら、予想とは違い、酸素が存在しないと反応が進まなかった。また銅は単量体から重合する場合と比較して添加量に対する効果が異なる傾向が見られた。
詳細は割愛するが、触媒の効果を「ポリマーが固体であるから」と言うのには少し解釈に無理があった。そんな状態だったが、ともかくポリフェニレンエーテルで分子鎖が伸び、連続疲労試験で可塑剤も含まれていないのに、分子量の増大が見られたので、一応、ポリフェニレンエーテルの実験に区切りをつけ、研究対象の高分子を変えることにした。
研究がこのような局面に達した時、研究の進め方には3つの選択がある。一つは、「既に探索的な結果が出たので、まったく別の研究に進む」ということである。科学は原理的な現象が確認できればそれで良いのだから、止めても良い。
キャベンディッシュならそうしただろう。彼は「論文を書くため」、「業績を上げるため」、「有名になるため」に研究したのではなく、単に興味があるものを研究し、それがわかったら急速に興味を失い、他の研究に進んだ人物だったからである。
万有引力に興味があり、初めて万有引力定数を測定した。それを自分の業績にする必要が無かった彼は、一度測定しただけで終わりにして、次の研究に入った。水素の発見、ヒ素の発見、比熱の法則、潜熱の発見、熱膨張率、電気の力と距離、電流の抵抗、誘電率などみな彼の発見によるものだ。
でも彼は「ああ、こうか!」と納得したら次の謎に取り組んだ。だから多くのことを発見したが、確認実験とか、再現性実験、最適化などには関心がなかった。科学とは本来、そういうものだろう。
私たちもキャベンディッシュなら「やはり人工的材料でも自己的に修復することは可能だ!」と喜んで、それで研究を終わりにしていたかも知れない。でも、それでは少し不満だった。「ポリフェニレンエーテル」でできたことを他の高分子でできないか?と考えたのである。
もう一つの進め方は「ポリフェニレンエーテルをもう少し研究し、実用段階までやろう」ということである。基礎研究から実用研究まではまた「深い谷」がある。触媒を入れると色が付くとか、湿気を吸う、ブリードする・・・などの欠点があるだろうから、それを一つ一つ潰さなければならない。その過程で有望と思われる技術も大半がその命を失う。
だから基礎研究で成功したからと言ってそれが直ちに工業製品になるものでもない。しかし、だからといって基礎的な技術が無意味でもない。新しい技術、新しい概念ができないと、新しい実用的なものも発生しない。大学は前段をやり、産業界が後段を担当するという役割分担は、双方の特徴を考えると良いのではないかと思っている。
ともかく、我々は「別のポリマー」に進むことにした。それはポリエーテルケトンだった。ポリフェニレンエーテルは一般的にはあまり知られていない樹脂だが、5大エンジニアリングプラスチックの一つだから何万トンという量が作られている。
それに対してポリエーテルケトンは「スーパーエンジニアリング・プラスチック」の一つで生産量は何千トン単位と一桁違う。そんなに珍しい高分子を使ってもどうかという考えもあるが、ポリフェニレンエーテルと似たところもあるので、それで行うことにした。
ポリエーテルケトンは、モノマーが“4-フルオロ-4’-ヒドロキシルベンゾフェノン(FHB)”、重合触媒が“炭酸カリウム”、重合溶媒が“ジフェニルスルフォン”という組み合わせで、320℃で重合する。化学構造は次のようなものである。
.jpg)
一方、重合して得たポリエーテルケトンを洗浄して乾燥し、一旦、パウダーとして取り出して、再び、再重合を試みた。企業の研究では研究対象とする物質が頻繁に変わることはない。
すでに商売として取り扱っている樹脂ならそれだけを研究するし、新しい樹脂の研究でもプロジェクトなどをつくって集中的にやるので、反応条件などは一定である。
これに対して大学の研究は、この前まで反応温度が40℃のポリフェニレンエーテルをやっていたのに、今度は温度が320℃のポリエーテルケトンである。貧乏なのに装置は全部しまい込んで、新しい装置を作らなければならない。だから大学の実験装置はいつも貧弱である。
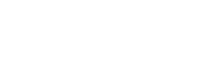
ポリエーテルケトンの研究を始めた頃にはポリフェニレンエーテルの経験があったので、高分子の劣化とその回復について、おおよそのイメージができていて、それは下の図のようなものだった。
.jpg)
高分子材料が何らかの理由で劣化する。そして分子鎖が切断する。実は研究の初期の頃、「分子鎖の切断」というのが劣化という概念と結びついていなかった。プラスチックなどの高分子材料はもともと「使い捨て」であったことや、色やニオイは注目されていても「力学的強度が長く保たれるか?」などは意識になかったからである。
だから「自己修復」というと「着色を抑える」などと捉えられた。人間で言えば「歳をとってもシワができない」というような感じであり、シワができても生存には関係がない。人工的材料で「生存」に関係がある性能というとやはり「強度」であり、それは「分子鎖の長さ」で決定される。
そこで上の図には「分子鎖切断」という表現が使われている。分子鎖が切断するとプラスチックが極端に弱くなって崩壊する。それを少し定量的に下のグラフで示す。これは衝撃強度が高いプラスチックとして有名なポリカーボネートの性能を示したものであるが、横軸が分子量、縦軸が衝撃強度である。
分子量が10万のもの(図では尺度が2のもの)は十分に高い強度を持つが、その分子量を少しずつ小さくしていくと3万程度のところで急激に低下し始める。
.jpg)
工業的に作られるプラスチックは、製品を成形する時、時間をできるだけ短くするために、溶かした高分子が「水のように」流れることを希望する。現実には水のようにはならないが、粘度を下げたいために分子量を下げて作られる。上の図で言えば崖っぷちギリギリの分子量で設計されるのである。
そういうことになると、使用している間に光、熱、力などで高分子鎖が切断されると、分子量が下がり、すぐ弱くなる。たとえば、高分子は長い鎖でできているが、真ん中が一つ切れただけで分子量は半分になるのだから、分子量が3万の物が切れると15,000になり強度は半分程度に落ちてしまう。
このことが、環境問題が起こる前まで、プラスチックがすぐ捨てられたり、リサイクルできない一つの原因になっていた。この状態のまま「一度、使ったプラスチックをリサイクルしよう」と言うことになったのだから材料の専門家の一人として心配したのも理解して頂けると思う。
つまり、「何とか使用後のプラスチックの分子量を上げて、リサイクルができるようにしたい」と思ったのである。私は「リサイクル嫌い」と思われているが、自己修復の研究はまじめにリサイクルを考えている研究者と捉えて欲しいと念願している。
それはともかく、ポリエーテルケトンの研究に取りかかった。でもまだ自己修復に疑問を感じていた。その一つが「キズができた」という情報が無くても修復剤は機能するのか?ということだった。これについては図の中に「情報」という言葉が入っていることでわかる。当時の不安が言葉になって現れているのである。
キズの情報が必要なのかについては機会があったら後に書きたいと思う。
おわり